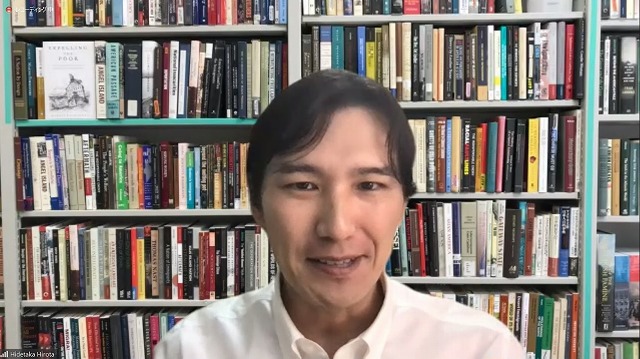主演・柳楽優弥、有村架純、三浦春馬の豪華共演で、”日本の原爆研究”を背景に、時代に翻弄されながらも全力で駆け抜けた若者たちの、等身大の姿を描いた青春グラフィティ『映画 太陽の子』が、7月10日(土)&17日(土)に上智大学英語学科主催のオンライントークイベントを開催。10日(土)は黒崎博監督をゲストに迎え、廣田秀孝氏(歴史学者/上智大学英語学科准教授)と対談し、映画における監督の視点、作品の歴史的背景についてなどを中心にトーク。17日(土)はL.A.を拠点に活躍する本作プロデューサー・森コウ氏をゲストに迎え、プロデューサーから見た映画業界の現状や未来に及ぶまで、幅広いトークが繰り広げられた。
かつて存在した“日本の原爆研究”。今までほとんど知られていなかったその事実を基に、若者たちが激動の時代でそれぞれの“未来”に向き合い選択してゆく姿を描いていることから、映画に登場する主人公たちと同世代の大学生に授業の一環として見せることができないかという提案から始まり、上智大学英語学科にて開催が決定。上智大学の学生と一般参加者も集まった。
★7月10日(土)
参加者:黒崎博(監督)、廣田秀孝(歴史学者/上智大学英語学科准教授)、ジョン・ウィリアムズ(映画監督/上智大学英語学科教授)
冒頭、司会を務めるジョン・ウィリアムズから、「作品が素晴らしく、演出が繊細で美術性も高い。そして、あまり話されていない、日本での原子の力を利用した新型爆弾の研究についての映画であり、この題材がとても面白いと思った」と本作を題材に選んだ理由に触れた。
日米合作というビッグプロジェクト誕生のきっかけは、今から10年以上も前に、広島県の図書館の片隅で若き科学者の日記の断片を見つけたことから始まる。そこには、研究のこと以外にも、当時の暮らしぶりや、あの子が好きだみたいな話も書かれていたという。彼らは秘密の研究室で暗い顔をして開発していたわけではなく、目の前にある未知の学問と向き合いながら懸命に生きていた、ということがイメージでき、是非彼らの物語を映像化したい、と決意したという。黒崎は、仕事の合間に様々な人々を訪ね各地をまわり、膨大な資料を集めた。2015年、渾身のリサーチを結実させたシナリオが、サンダンス・インスティテュート/NHK賞を受賞、大きな一歩を踏み出した。しかし、高く評価された壮大な世界観とセンシティブなテーマが、映像化実現へのハードルを上げていた。それでも一切の妥協を許さず、映画化を意識してむしろスケールを膨らませたシナリオをプロデューサーの土屋勝裕に渡した。シナリオを読んだ土屋は、「非常に力がある」と感服すると同時に、海外との共同製作が絶対条件だと判断、潤沢な製作費の獲得はもちろんのことだが、自分たちメディアが語り継がねばならないテーマがあると感じ、また、戦争で原爆を落とされた唯一の国である日本が、実は加害者にもなり得たかもしれないという深い視点を世界に問いかけたいと考えたという。こうして様々な人たちの情熱が結実して、映画は完成した。

―フィクションの現場で生まれたドキュメンタリーを撮る!黒崎のこだわった演出
ドキュメンタリーや子供向け番組、教育番組の制作も行いながら、ずっと映画を撮りたいと願っていた黒崎にとって、本作は長編2本目。
祖父が、ラジオドラマの脚本家で、仕事を始める頃にその脚本を手に取ったら初めてそれが面白いと感じ、フィクションとして人に伝わるものは非常に面白い、と思い、今の仕事に至ったという。
本作の演出に感銘を受けたジョンから、まず演出について聞かれると、黒崎は「フィクションは、つくりもの。脚本という設計図があり、作為がある嘘の世界。けれども、それは手段であって、本当の気持ちを伝えられたらいいなと思って作っているのがフィクション。」と置いた上で、「俳優は脚本に沿って演じているが、時として、笑わなければいけないところで泣いてしまったり、涙を流す予定だったシーンで笑顔がこぼれたり、人間は、予期せぬことが生まれてくるもの。それを設計図に戻そうと歪めるのではなく、とにかくそれを撮ってみよう、と思っている。フィクションであっても現場で生まれたドキュメンタリーを撮っているんだと、それを取りこぼしたら一生撮れないから、そういう緊張感をもって臨もうと、現場で話していた」と、繊細な映像を生み出した演出について明かした。また、脚本については「この映画を暗い物語と決めつけるのはやめようと思っていた。 若者たちの物語なのだから、とってもエネルギーにあふれているだろうし、一色(いちいろ)に決めないで、色々な表情を取り込もうと思った」と、戦争の時代だからこうだ、と決めつけない考えであったことが分かった。

―“原子の力を利用した新型爆弾”の研究をめぐる葛藤、戦争映画の描き方への挑戦
続いて廣田から、“日本の原爆研究”というトピックを知り、映画の制作においてこの事実に関する理解をどう深めていったのかを問われると、「(専門分野でもないので)分からないことだらけで難しかった。文献がないか、この件について調べている大学の先生がいないか、などを調べることから始めてた。しかし、当時在籍していた人たちはほとんどなくなってしまっていて辿り着けなかったが、一番若手の研究者を知ることができて、手紙を書いた。なかなか返事をいただけなかったので無理だったかな、と思っていたころ、親族から電話をもらい、手紙の相手は高齢でなくなってしまっており、未開封の手紙が残っていたのを発見して連絡をしてくれた。すぐに会いに行ったところ、
実験ノートやメモ、戦後に回想して描いた文章をいくつか見せてもらうことができた。戦後2年ほど高校の教師をして、その後は、晩年まで物理学者として生きた、ということで、それを参考にして、主人公の姿を作っていった」と、調べることから始まった本作の苦労の一端に触れた。
次に、日本軍が新型爆弾のアイデアに着目し、京都帝国大学がその任務を受けることになった歴史的背景について聞かれると、「大事なのは、最初から原爆を作ろうと思って研究していたということではない、ということ。当時、最新の学問であり、ドイツとオーストリアの科学者によってウランが核分裂することが発見され、分列するときに膨大なエネルギーが放出されているのではないか、という議論に科学者たちがこぞって飛びつき、研究が進められていった。しかし、第二次世界大戦が始まると、科学者たちのネットワークが遮断されてしまい各国が何を研究しているかわからなくなってしまっていたが、核分裂が大きなエネルギーを生むことは理論的には分かっていたので、、海軍が荒勝教授へ命令を下した。これが海軍と京都帝国大学の関係、といえる。ただ、学生たちにとっては、核分裂の研究という純粋は物理学の研究だったものが、兵器開発の研究にすり替わってしまうというショッキングな出来事だった」と、当時の学生たち感じた驚きや、葛藤などにも思いを寄せながら話した。
また、研究室の学生たちは、大量破壊兵器を作ることや、科学や戦争、政治的なことへの意見や考えが変わっていったことはあったのか?という問いについては、「一番センシティブで、難しいことだと思う。フィクションの中での、戦争の描き方は難しい。日本の中では、特に原爆については犠牲者側に立っている物語が多いが、それだけでは戦争の実態は描き切れないだろうと、いう思いがあった。誰でも加害者、にも被害者にもなる可能性がある、普遍的な視点で物語を作りたいと思っていた」と、戦争映画の描き方への挑戦もあったことに触れ、
「当時の学生や若い研究者たちが、殺戮兵器を作ることついて、どのような議論をしたかは、記録が残っていないため分からない。
皆、戦後は、『科学が加担することには反対する』と言えるけれど、当時は、戦争に協力することは正義だ、という考えも当然あっただろうとも思うし、判断するのは難しく、どちらの視点も持っていたと思うので、それを映画の中に織り込んだ。」と、研究者たちの思いを探りながら作っていったことが分かった。
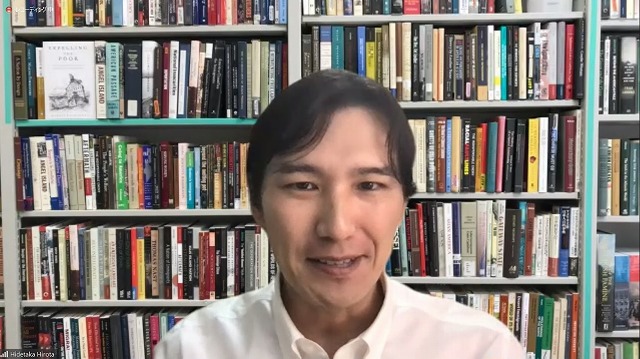
―科学が開くと信じてきた“未来”は今どうなっているのか、本作が現代の人へ問いかける“未来”とは?
話は映画のテーマへと移り、本作の重要なテーマの一つが「未来」ということでそれをどのように位置づけたかを聞かれると、科学者の兄・修と、軍人の弟・裕之に思われている幼なじみの世津に触れ、「未来を見据えているのが、世津という人物で、この物語のなかで大切な存在。当時、男性が強くて女性が虐げられているいう文化だったと思うが、原始的に“生きてないとだめでしょう”と、世津(に代表される)女性が言ってくれることが、人間にとって強いことなのではないかと思った。当たり前に大事なことをまっすぐに言ってくれる女優さんが僕にとっては必要で、それが有村架純さんだった。」と、世津にまさに台詞を託したエピソードが明かされた。
「国家のために何かをやるんだと、いうことが正しいかどうかは後にならないと分からないけれど、“未来を見ていかないとだめでしょう、生きていく意味がないとだめでしょう”と、当時が歪んでいたことがわかる今の時代を生きていて、今(作品を)見るのは僕達なので、だからこういうセリフを言ってもらった。昔を語る映画ではなくて、未来を語る映画として撮っていた」と、まさに、今を生きる私たちが受け止め考えることがテーマの“未来”にこめられていることも、力強く語った。
イベントの終わりに、参加者からの質問で、「中立的な視点からの物語を作るためにした工夫」を聞かれると、「研究者たちの実験ノートはドイツ語や英語で書いていた。いっぱい情報交換をしてやりとしていた。アメリカ、イギリス、ドイツ、フランスにも協力体制があった。交流あってこその科学者、ということが当たり前だった。ただの敵、とは思っていなくて、いっぱい友人もいた。そういうことから、その感覚にのっとっていけば、軍部が一般市民に言っていたような感覚とは違うところから、描いていいけるかなと思った。困るときは、科学者が日記を書いていた感覚に立ち戻っていた」と、登場人物たちの感覚に寄り添って、物語を紡いでいったことを明かした。

8月6日(金)、未来へ
★7月17日(土)のレポートはこちら